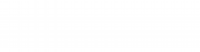氷河の魅力
氷河は格好の撮影対象だ。「数千年や数万年」のタイムスケールで物事を想像してみること、それは現代に生きるものとして必要なスキルだと思っている私としては、約2万年前に最終氷期を迎えた氷河の姿は、雄弁に時の移ろいを物語ってくれるからだ。また、世界を循環している「水」が数十万年やそれ以上の単位でストップ&ゴーを繰り返している物語も壮大で好きだ。
氷の塊であり、ツルツルのくせにガッチガチに固い氷河での撮影は、油断は禁物。アイゼンを付け、ピッケルも持ち歩いているが、三脚とカメラを担いだままでは思ったように歩けないことの方が多い。
転ぶと目がチカチカするほど固いし、形は複雑で真っ直ぐには歩けない。クレバスとよばれる深い裂け目に落ちてしまえば這い上がることは難しく、四方から吹いてくる冷たい風からは逃げ場も見つからない。
這うように氷河の上を歩き、氷河のトンネルを見つけ、中に潜り込む。
外と比べるとその中は驚くほど静かで、青一色に包まれた氷の世界が広がっている。その空間に五感が慣れた頃、足元で静かに流れている水音が耳を刺激する。トンネルのすこし奥では、その流れに滴が落ちている。この静謐さは写真でも伝わるだろう、そう思いながらシャッターを切った。
見かけや色の美しさだけでなく、今も世界のどこかで融け、空間的にも時間的にも、遠いところへ我々の想像を運んでくれることも氷河の魅力だ。

固体から液体へと姿を変える氷河。数万年ぶりに地球の水の循環へと戻ってゆく。
この滴が落ちる瞬間から、水の長い旅が始まる。

氷河にマクロレンズで寄って撮った写真。氷河をよく見ると、氷に閉じ込められた空気の通り道が見える。
数万年前に氷河の中に取り残された気体は、少しづつ大気の循環へと戻っていく。
縄張り争い
北極圏での撮影中、捨てられた小屋(と言っても2辺は壁もなかったが)で3泊過ごしたことがあった。
そこはリスの縄張りの中間点なのか、2匹のアカリスが追いかけあい、攻防を繰り返していた。
しかし、その様子を微笑みながら見ていられたのは初日だけ。そこから数日、彼らの縄張り争いに加わることになったからだ。
翌朝、廃棄された洗濯機(と言っても半分はなぜか溶けていたが)に入れていた食料ザックには穴が開けられ、置き土産までされていた。
アカリスの仕業だ。
幸い致命的なダメージではなかったので、その夜は少し離れたところにある車(と言ってもほぼ車の形は成していないほどボロボロ)の運転席に隠した。が、それもダメだった。ごちそうさま、と言わんばかりにまた置き土産も。くそう、と思わず声が出た。
パスタなどのメインの食材は熊用のフードコンテナに入れてあるので無事なものの、軽視していては命に関わる。その日は撮影に出ず、小屋の周りをうろつくアカリスを、小屋の中にひっくり返っていた棚の引き出し(と言っても4段のうち2段しか引き出しはないが)に閉じ込めることにした。
貴重なパンのかけらを使い、半分開けた引き出しにおびき寄せる。アカリスは、基本的にはじっとしているとこちらの存在には気づかないのだが、私の気配(半分殺気)を察するのか、何度か逃げ、また戻って来ることを繰り返した。1時間弱ほど経っただろうか、安心したらしい、引き出しの中のパンに気づき、飛び込んだ。
ここぞとばかりに駆け、引き出しの入り口を蹴る。勢いよく引き出しが閉まる時、引き出しの奥へ隠れるリスのお尻が見えた。
成功だ。
貴重な半日と食材を使い、私は一時的に縄張りを獲得した。
しかしほっとしたのもつかの間、翌日、もう一匹のリスと戦うハメになってしまう。



タイガの森に入ると、必ずと言っていいほどアカリスの警戒音が聞こえる。危険はないが、関わり方次第だと改めて感じた。ちなみに、彼らは冬眠しない。驚くことに、この小さな体でー40℃の冬を越えるのだ。
装備について
よく聞かれるのが、どんな装備を持って撮影しているのか、ということ。
ことアラスカに関して言えば、学生時代に読み漁った星野道夫さんの美しい文面の端々から得た知識。それに加え、北アルプスで過ごした時間や西表島でヤマネコを追いながら得た体験、それらに、事前の調査を加えて装備を準備する。
フィールドワークはほぼ一人で行うので、場合によって異なるが、例えば夏のアラスカでは、約50キロ程度の装備や機材や食材を背負っている。背中には75リットルのザックと、おなかにはカメラバックを抱えるスタイルが多い。水が手に入らなそうなエリアであれば10リットル以上の水を背負うことも。
また、氷の上を歩く季節・エリアになれば、ザックではなくソリに乗せて運ぶのだが、マイナス40度にも耐えられる装備のぶん夏より重くなり、おそらく80キロ前後あると思われる。
機材はカメラのボディが2台、レンズは6本ほど。望遠のレンズは一本2キロほど。その他、三脚、レリーズ、大量のバッテリー、データカード、時にはノートパソコンも。機材は一番重いが、時には自分より大事に扱わなくてはいけない。
装備はテント、雨具、ファーストエイドキットやガスコンロ、燃料、寝袋や着替えや防寒具などなど。撮影前に装備を選ぶのだが、これがないと危険かな、と思い始めると置いていけず、そびえるようなザックになってしまい、原野に入ってから後悔することも多い。
食材は、軽さが最優先で、その次に、茹でて済むもの、というくくりで考える。油ものは匂いも強いし、食器を洗う水が十分でないことも多い。パスタやフリーズドライのものや乾麺・乾物などは軽いし凍らないので、重宝する。街に買い出しに出た後は食材も豊富なので、数日の間はソーセージや生野菜などが食べられ、原野の中でとても豊かな暮らしをしている気持ちになれる。

この写真で10日から2週間分ほどの装備。重さは50キロほど。大好きなベーグルは朝食の定番。
ツンドラでは野生のブルーベリーもたくさんあるので山ほど食べる。

自分の体に入れたものが感性に影響することはわかってはいるのだが、撮影中はとりあえずお腹
を満たし、そのエネルギーで自分がどれだけ動けるか、無機質に考えてしまうことも多い。
廻っている
みんなに「地球」を感じてほしい。とりわけ「地球が廻っていること」を感じてほしい。いつからかそんなことを思うようになっていた。
振り返ると色褪せずに残っている思い出がいくつかある。
山小屋で働いていた時、日の出を見て涙しているお客さんの顔。
大都会の駅で、改札にひっかかってしまった私を殺気を込めて睨みつけた後ろの人の顔。
心のままに生きるということを教えてくれたうちの犬、ムギ。
パソコンの画面ばかり見つめ、散乱している情報に振り回されたあげく命を絶った友人。
何が自分の覚悟を決めさせたのか定かではないが、ある時、心が決まったのを感じた。
「伝えよう」と。
自分にはできる。とも感じた。
数千年、数万年を彷彿とさせる世界を伝え、地球を感じてもらおう。どんな立場やどんな考え方の人にも平等に届く「地球が廻っている」という真実は、誰の心にも安心をくれるはずだ。様々な命や、水や、風、我々の感情さえも内包して廻り続けることを意識の片隅に置いておけたら、いま眼前にあるものに安心を奪われたりはしないだろう。
みんなが安心している世界は、きっと今より美しい。
覚悟が決まると、冷静と情熱が私の中に宿り、恐れるものは無くなった。原始性の高い世界とそこに生きる生き物たちを撮影し、発信していこう。問題は少なくはないだろうが、私は私にできることをやるだけだ。

太陽はいま、どこかでのぼり

そしてまた、いまどこかで沈んでいる
好奇心と想像力
原野で撮影していると、時折、私の想像の幅を広げてくれる出来事が起こる。
何日も原野を歩き回り、野生生物に会いたくても出会えないことも多いのに、時折、彼らの方か
ら興味を示して寄ってくることもあるのだ。
ある時、クマに襲われかけた30分ほど後のこと。さっきの事で敏感になっていた私は、できるだけ見晴らしの良い場所を見つけ、右手にはベアスプレーを握りしめ、降ろしたザックに腰をかけていた。ツンドラでは、目線次第で得られる情報量が圧倒的に違うので、少しでも高いところにいることが肝要なのだ。
呼吸が整い、冷静さを取り戻すと、敏感になった五感がさらに鋭くなる感覚を得た。この感覚がある時は恐怖心も薄れる。動物より先に彼らを見つけられる(気がする)からだ。
その数分後、200メートルほど先だろうか、森の際で、何かが動いた。
そっと双眼鏡を覗く。
カリブーだ。
少しほっとして、ザックからカメラを取り出す。気づかれればすぐに逃げてしまうので、這うように彼に近づいた。
しかし、あと50メートルほどのところで私は彼の目に捕らえられてしまった。
ああ、逃げてしまう。
そう思いカメラを構えようと体を少し持ち上げると、キョトンとしたような表情の彼と目があった。
一瞬の静寂のあと、彼は、こともあろうに、私に近づいてきた。首を上げ下げしながら、円を描くように、私を観察するかのように、足音、鼻息まで聞こえるわずか数メートルのところまで。
私は野生生物の動きのしなやかさと筋肉質な肢体にすっかり目を奪われていたが、ハッと我に返ってファインダーを覗いた。数枚シャッターを切ると、私に興味をなくしたのだろうか、彼は振り向くことなく、飛ぶように去っていった。
彼らの好奇心によって、私の想像や常識の壁を壊してくれる瞬間はなんとも心地いい。そしてその時生まれる新鮮な想像力は、新しい好奇心へと繋がってゆく。

鼻を鳴らしながら近づいてくるカリブー。歩きにくいツンドラをものともせず、飛ぶように歩く姿
はとても美しい。この個体の体長は角の先で約150センチほど。

私が動くとすぐ水中に潜ってしまうが、じっとしているとまた近づいてきて様子を伺う小さなビー
バー。どの動物も、やはり子供たちの方が好奇心が強い。この個体で、5~60センチ。

シラガマーモット。雪が降った翌日、日向ぼっこをしているとき、何かに見られている気がして、
気配の方を見ると彼がいた。岩の陰には巣があり、家族もいた。